「植物は、夜の長さを計って、ツボミをつくり、花を咲かせる」ことを紹介してきました。では、植物は、葉、茎、芽、根の、どの部分で、夜の長さを計るのでしょうか。
それを知るために、アサガオの芽生えを、電灯をつけっぱなしにした照明のもとで育てます。アサガオは長い夜を感じると、ツボミをつくります。そこで、葉、茎、芽、根のいずれかだけを黒い紙でおおい、ツボミをつくるような長い暗黒を部分的に与えます。
すると、葉をおおった場合だけ、ツボミができます。つまり、葉が、ツボミをつくるために必要な夜の長さを感じるのです。多くの植物が、発芽したばかりの芽生えの葉でも夜の長さを感じます。
たとえば、アサガオでは、タネが発芽したばかりのふた葉(子葉)の葉に、夜を感じる能力がすでにあります。そのため、子葉に長い夜を与えると、小さな芽生えにツボミをつくらせることができます。アサガオだけでなく、植物がツボミをつくるために夜の暗黒の長さを計るのは、葉なのです。
では、ツボミは、植物のどの部分につくられるのでしょうか。この疑問をもって、植物を観察すると、ツボミは芽でつくられることがわかります。芽からは、葉もできますが、ツボミも芽でつくられるのです。葉をつくっている芽を「葉芽」とよび、ツボミをつくった芽を「花芽」とよびます。
植物がツボミをつくるために必要な夜の暗黒の長さを計るのは葉であり、ツボミができるのは芽なのです。葉と芽は、別々のもので、離れています。とすると、ツボミをつくるために必要な夜の暗黒を感じた葉は、芽に「ツボミをつくるように」という合図を送らなければなりません。動物のような神経をもたない植物は、どのようにして、葉から芽に合図を送るのでしょうか。
1936年に旧ソ連のチャイラヒアンは、「ツボミをつくるために必要な夜の暗黒を感じた葉は、葉の中でツボミをつくらせる物質をつくり、それを芽に送る」という仮説を提唱しました。その物質はフロリゲン(花成ホルモン)と名づけられました。
そこで、世界中の多くの研究者が、ツボミをつくるために必要な夜の暗黒を感じた葉から、フロリゲンを取りだそうと試みました。しかし、チャイラヒアンの提唱以来約70年以上を経ても、フロリゲンを取りだすことに成功しなかったのです。そのため、「幻のフロリゲン」と呼ばれ始めました。
ところが、近年、フロリゲンの正体が明らかにされてきました。次回に紹介します。

田中修著「植物学『超』入門」より
(サイエンス・アイ新書 SBクリエイティブ株式会社)









Guest Columnist
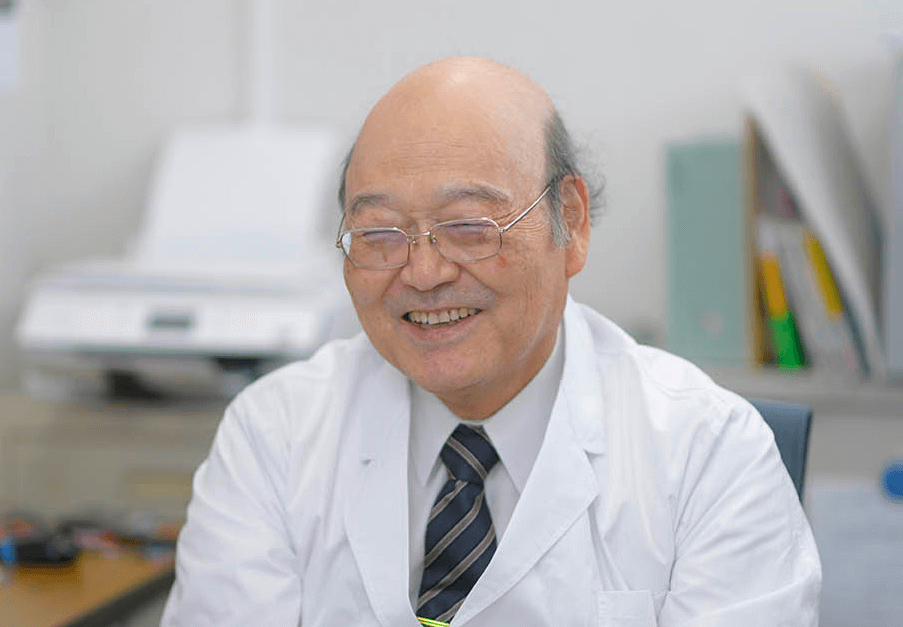
田中 修
TANAKA Osamu
農学博士、専門は植物生理学。
甲南大学特別客員教授。
京都大学大学院博士課程修了。
スミソニアン研究所(アメリカ)博士研究員などを経て現職。
植物と人との関わりなどについて、テレビやラジオなどで解説。
著書:『植物のひみつ』『植物はすごい』『雑草のはなし』『ふしぎの植物』『日本の花を愛おしむ』(中央公論社)、 『フルーツひとつばなし』(講談社現代新書)、『植物は人類最強の相棒である』(PHP新書)、『植物のかしこい生き方』『植物学「超」入門』(SBクリエイティブ)など多数。

